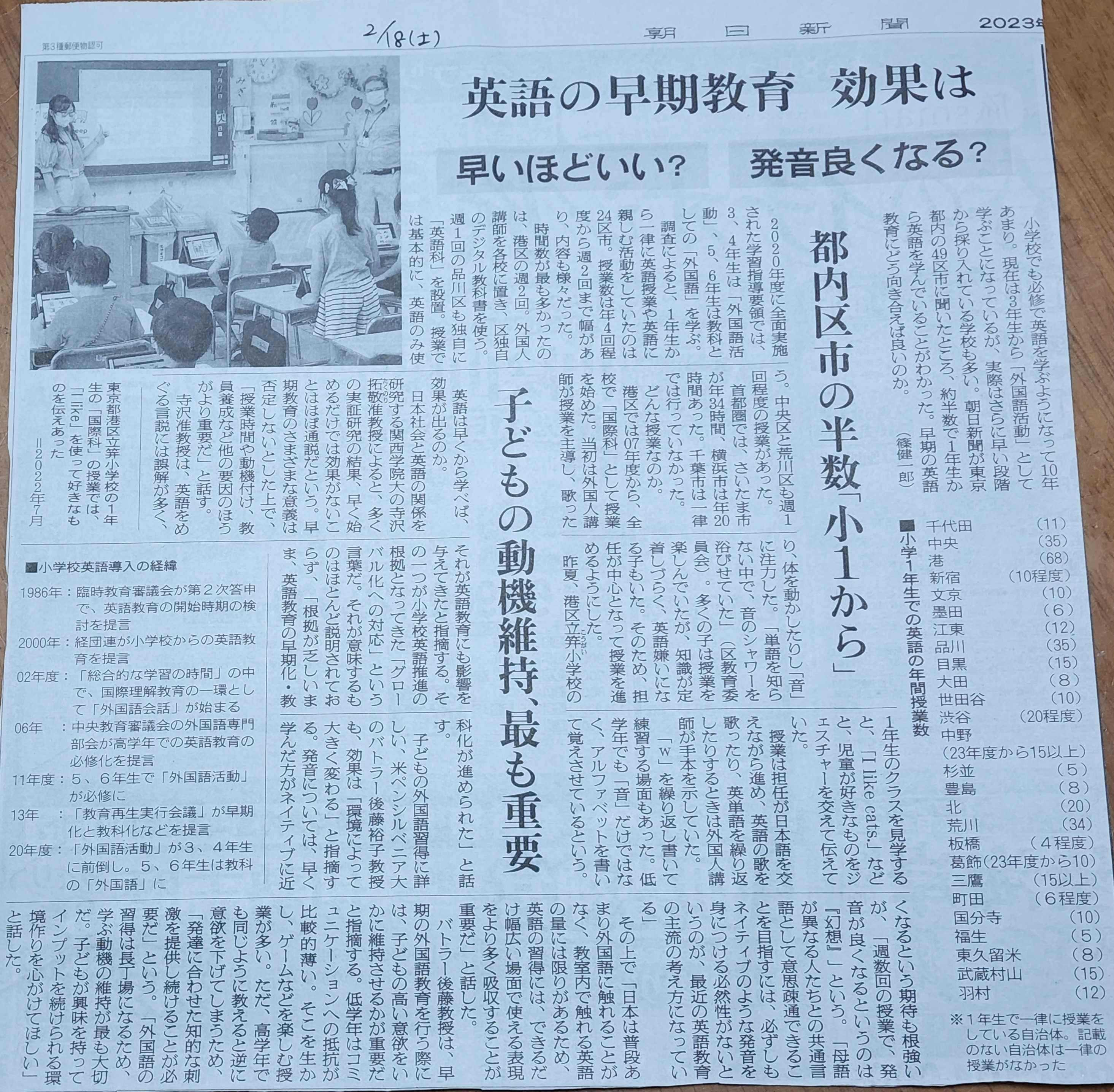子どもの習い事で大変人気のある英語。しかしその効果を疑問視する声が多数あるのも事実です。
「効果云々ではなく、子どもが楽しそうに通っていればいいのでは」と考える保護者がいる一方で、「早期英語教育を行って子どもをバイリンガルにする」と鼻息の荒い保護者もいます。
子ども側は「頑張ると大人が褒めてくれるから」と単純な理由かもしれません。
早期から英語教育を行うことは、本当に子どもにとって効果があるのでしょうか?
文部科学省「小3から外国語活動」→東京都内区市では「約半数は1年生から」
2020年度に全面的に実施された学習指導要領では
・5,6年生:外国語 成績が付く
・4年生:外国語活動 成績は付かない
となっています。
しかし、1年生から何らかの形で英語を取り入れているのは24市区にものぼりました。
授業数は年に4回程度から週2回までとかなりの幅もありました。
実際にどんな授業を行っているのでしょうか。
英語の歌をうたったり「音」に注力した港区では、児童が楽しんで参加している一方で、知識が定着しづらく、英語嫌いになる子もいたそうです。
そのため担任が中心となって授業を進める形に変更したそうです。
現在は、児童が好きな物をジェスチャーを加えて伝えたり、英単語の練習をしたりしています。
最も大切なのは「子どもの動機の維持」
関西大学で日本社会と英語を研究する寺沢拓敬教授は、多くの実証実験の結果、早く始めるだけでは効果がないことがほぼ通説となっているそうです。
早期教育に全く意味がないことはありませんが、「授業時間・動機付け・教員など、他の要因の方が重要」とのことです。
さらに、「英語をめぐる説には誤解が多く、それが英語教育に大きな影響を与えてきた」と指摘しています。
その一つとして挙げられるのが「グローバル化への対応」という言葉。ほとんど説明をされないまま、英語の早期教育化だけが先走りしてしまったいるようです。
週に数回の授業で「発音が良くなる」は幻想
テレビCMで子どもが流暢な発音で英語を話しているのをよく見ますね。でも週に何回かの授業で発音が良くなることは難しいそうです。
それよりも、「母国語の違う人たちと英語で意思疎通するには、必ずしもネイティブのような発音である必要はない」というのが最近の考え方だそうです。
また、できるだけ幅広い場面で使える表現を多く吸収していくのが理想とのこと。
さらには、子どもの高い意欲を以下に持続させるか。これが最も重要だそうです。
子どもが興味を持ってインプットを続けられる環境作りが最も大切とのことでした。
早期に英語を習わせている保護者を否定しているわけではありませんが・・・
幼少期に英語ができるようになると、大人に褒められたり自分に自信が付いたりなど良い面もたくさんあります。英語の学習を通じて自己肯定感太高まるのであれば、とても効果があるのではないでしょうか。保護者も子どもが楽しんで英語に接しているととても嬉しいですし誇らしいですよね。
ただ、それがそのまま大人になるまで持続するかどうかは子ども次第。
「子ども習い事」という割り切りも必要なのでは、と感じました。
ただ、共働きが多い昨今、子どもに習い事をさせる時間がなかなかない!と嘆いている保護者のかたもいるのではないでしょうか。
そんな時がベビーシッターやキッズシッターサービスにお願いするもの一つの手です。
悩んでいたら子どもはどんどん成長していってしまいます。気になったらアクセス!
2023年2月18日(土)朝日新聞朝刊より出典・引用しています。